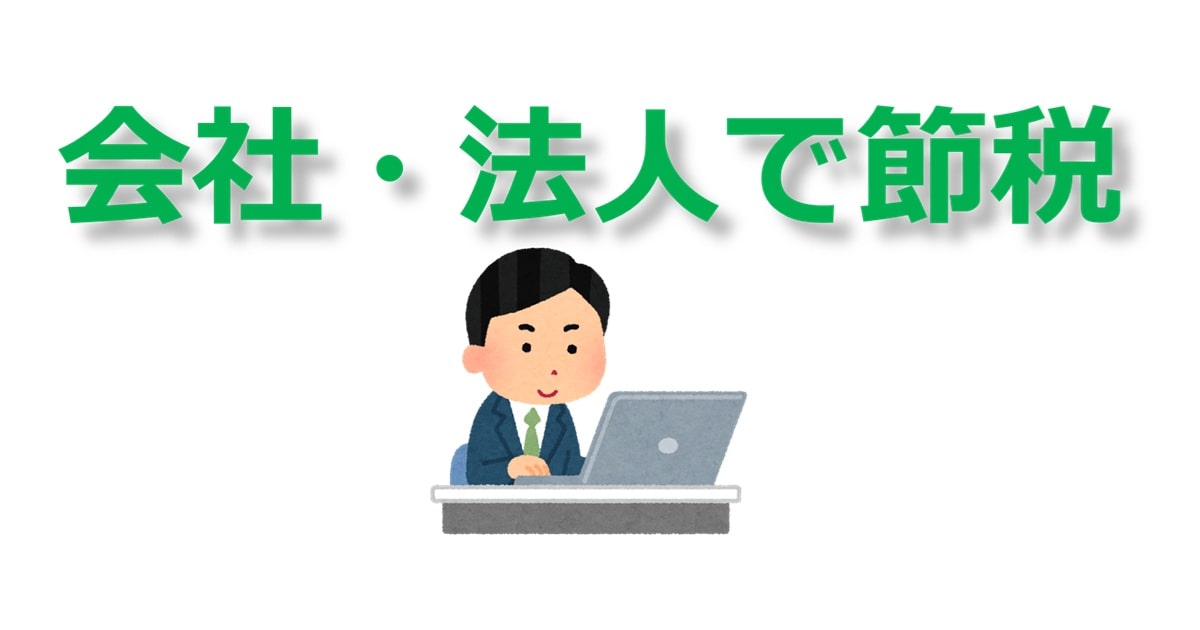サラリーマンが事業を始める場合、個人名義で事業を行う個人事業と、会社をつくって事業を行う法人事業の2通りがあります。法人で事業を行うメリットは、何と言っても大きく節税できることです。
本来、会社とは個人ではできない大きな事業をするためのものですが、日本の多くの小さな会社は税金を安くするためにつくられています。
サラリーマンが副業で節税する方法は、副業所得の金額によって変わります。
- 副業所得が約500万円までの個人事業主の場合
- 副業所得が約500万円を超える法人の場合
この記事では2の「法人の場合」について説明します。
個人事業と法人の違い
個人事業と法人の違いを表にまとめました。
| 個人事業主 | 法人 | |
| 事業開始までの手続き | 開業届 | 法人登記、定款 |
| 設立費用 | 0円 | 法定費用 合同会社10万円~ 株式会社25万円~ |
| 資本金 | 0円 | 1円~ |
| 事業維持の費用 | 特になし | 赤字でも法人税7万円 社会保険料の企業負担 法人税申告書、決算書で税理士費用(自分ですれば税理士費用はかからない) |
| 税金 | 所得税(累進課税) 個人住民税 個人事業税 消費税 | 法人税(比例課税) 法人住民税 法人事業税 消費税 |
| 経費の範囲 | 事業にかかった費用 交際費 | 事業にかかった費用 交際費 経営者や社員の給与 福利厚生 社宅の家賃 出張時の日当 生命保険料(法人契約) |
| 交際費 | 制限なし | 800万円まで(資本金1億円以下の場合) |
| 事業主の給与 | 経費にならない 給与という概念はなく、売上から経費や社会保険料などを差し引いて残ったものが事業主の所得となる | 経費になる 法人から支払われる |
| 給与所得控除 | 代表者は事業所得者のため、給与所得控除なし | 法人からの給料に給与所得控除あり |
| 家族従業員の給与 | 税務署にあらかじめ給与額の届け出が必要 | 毎月一定の給与額なら届け出不要、損金算入可能、配偶者控除や扶養控除は収入が低ければ可能 |
| 社会保険の加入義務 | 従業員5人未満なら、なし | あり(社会保険料負担発生) |
| 赤字の繰越 | 3年(青色申告) | 10年 |
| 責任範囲 | 無限責任 | 有限責任 |
| 社会的信用 | 小さい | 大きい |
個人事業主は事業の利益はすべて事業主のものとなり、事業の利益に所得税がかかります。しかし法人の場合は、事業の利益を法人の利益(法人税)と事業主の給与(所得税)にわけることができます。この仕組みをうまく使えば法人では税金を大幅に下げることができます。
例えば売り上げが2,000万円で経費が1,000万円の法人があるとします。利益は1,000万円です。
これが個人事業主の場合、利益の1,000万円がそのまま所得となり1,000万円に対して所得税がかかります。
一方、法人の場合は1,000万円の利益を事業主やその家族従業員に給与として分配して会社の利益をゼロにして法人税を無しにすることができます。事業主やその家族従業員の給与も1,000万円を分散させて所得税を安くすることが可能です。
会社をつくって節税する方法
さまざまな経費

会社の税法上のメリットは、会社にはさまざまな経費が認められていることです。法人税や法人事業税といった会社の税金は、会社の利益に対して課されます。会社の利益は売り上げから経費を引いたもので、経費が多ければ税金を安くできます。
例えば、車を会社の業務で使用するなら会社の経費で購入できます。それが高級車でも問題ありません。車は会社の名義でも、実際に使うのは自分なので自分が購入したのと同じように使用できます。
交際費

中小企業の社長がたくさんお金を使える理由は、自分のお金に加えて会社の経費を使えるためです。特に交際費は年間800万円まで使うことができます。
税務署はよほどのことがなければ接待交際費の相手まで細かく調べないため、実質的に接待交際費は自由に使えます。売り上げを超えない範囲で、ですが。
交際費として認められる主な支出
- 接待などの飲食代
- 交流会やイベントへの参加費
- お中元やお歳暮
- ご祝儀や香典
- お車代
- 取引先への商品券やギフト券
- 取引先との旅行代
- 接待ゴルフ
- 取引先へのお土産などの贈答品
- 会食、宴会費用
旅行費用

純粋なプライベートの旅行を経費にすることはできませんが、事業に関係のある出張なら経費にできます。この「出張」を最大限に拡大解釈することで、旅行代金を経費に計上することができます。
例えば不動産経営をしている場合は不動産の下見調査であったり、ネットで商品を販売している場合はネットで販売できる商品の調査といった名目で「出張」できます。
家賃
会社が社員のためにマンションを借り上げる費用や社宅を購入する費用も経費にできます。これは社員にとって税金のかからない給料とみなせます。ふつうは自分の給料から家賃を支払いますが、給料は受け取った時点で税金を取られているため、家賃には税金が課せられているようなものです。会社の経費で家賃を出せると節税できることになります。
ただし、家賃の全額を会社が負担すると給料と同じ扱いになってしまうため、社員は家賃の15%程度を支払う必要があります。これでも十分節税になります。
昼食代
会議費で昼食代を出すことができます。出前や忠司を利用することも、どこかレストランを利用することもできます。
ただし、会議費として支出する場合は、議事録などの記録を残しておく必要があります。
夜食代
残業した社員の食事代を会社が負担した場合、そのお金は給料として課税しなくていいことになっています。出前や仕出しを利用して経費にすることができます。
家族経営

日本には家族だけが社員の会社もたくさんあります。
例えば、売り上げが3,000万円で、社長と社員が家族だけの会社があったとします。この会社では利益のすべてを社員の給料にします。所得税は累進課税なので、家族社員ひとりひとりの給料は多くせず、できるだけ均等にして所得税率を下げます。
妻や子供は会社から給料をもらいますが、扶養から外れない金額に抑えているために扶養控除などの特典はきっちりもらっています。
この会社では儲かった年は社員である家族に臨時ボーナスを出したり経費で車を買ったりして会社の利益をゼロにします。会社の利益がゼロになると法人税が免除されます。
このようにすると、税金を節税したうえで、家族全体の手取りを最大化したうえで会社の経費を使って優雅な暮らしをすることができます。
このように家族経営の会社では利益を出すと税金が増えるだけなので、会社を黒字にする動機がありません。ただ、銀行から融資を受ける場合は経営状態が黒字である必要があるため、多少の黒字にはするかもしれません。
サラリーマンが会社設立で節税できる2つのケース
サラリーマンが会社を設立することで節税できるケースはありますが、節税につながるケースは限定されています。全てのサラリーマンが会社設立で節税できる訳ではありません。
副業していて「事業所得」がある場合
サラリーマンでも副業の利益が多くなり、課税所得金額が500~600万円になると法人化することで節税できるようになります。個人で所得税を支払うより法人で税金を支払う方が安くなるためです。課税所得金額とは、1年間の収入から経費や所得控除などを差し引いた金額です。
表を見ると、課税所得金額500万円から600万円の間で、会社設立による節税メリットが出てくることがわかります。
個人と法人の概算税額比較表
| 課税所得金額 | 個人 | 法人 |
| 所得税額など | 法人税額など | |
| 1,000,000円 | 86,000円 | 283,600円 |
| 2,000,000円 | 237,000円 | 497,200円 |
| 3,000,000円 | 424,200円 | 710,800円 |
| 4,000,000円 | 705,700円 | 924,400円 |
| 5,000,000円 | 1,059,900円 | 1,156,100円 |
| 6,000,000円 | 1,414,100円 | 1,378,800円 |
| 7,000,000円 | 1,768,300円 | 1,619,500円 |
| 8,000,000円 | 2,144,400円 | 1,851,200円 |
※住民税均等割として個人5,000円、法人70,000円を合算しています。
※人的控除の差額調整額として個人の税額から2,500円控除しています。
不動産投資をしていて「不動産所得」がある場合
本業の仕事以外に不動産投資をしていて不動産所得があるサラリーマンも、会社を設立して節税することができます。不動産投資で法人化する規模は、課税所得金額が900万円を超えたタイミングが一つの目安となります。
また、不動産所得は給与所得と合算できるため、不動産所得がマイナスの場合は会社を設立せずに個人事業主として確定申告するだけで節税できます。

損失が出るような投資ならしないほうがましですが・・・
会社をつくれば相続税も節税できる
普通の相続の場合は、亡くなった人の資産を時価で計算し、相続した人は相続した金額に対して相続税が課されます。一方で自分の資産を会社に移していた場合、相続人は会社の株式を相続します。
経費をたくさん計上して赤字にしている会社は資産価値が低くなるため、相続税が安くなります。さらに、事業承継円滑化のための税制措置を利用することもできます。