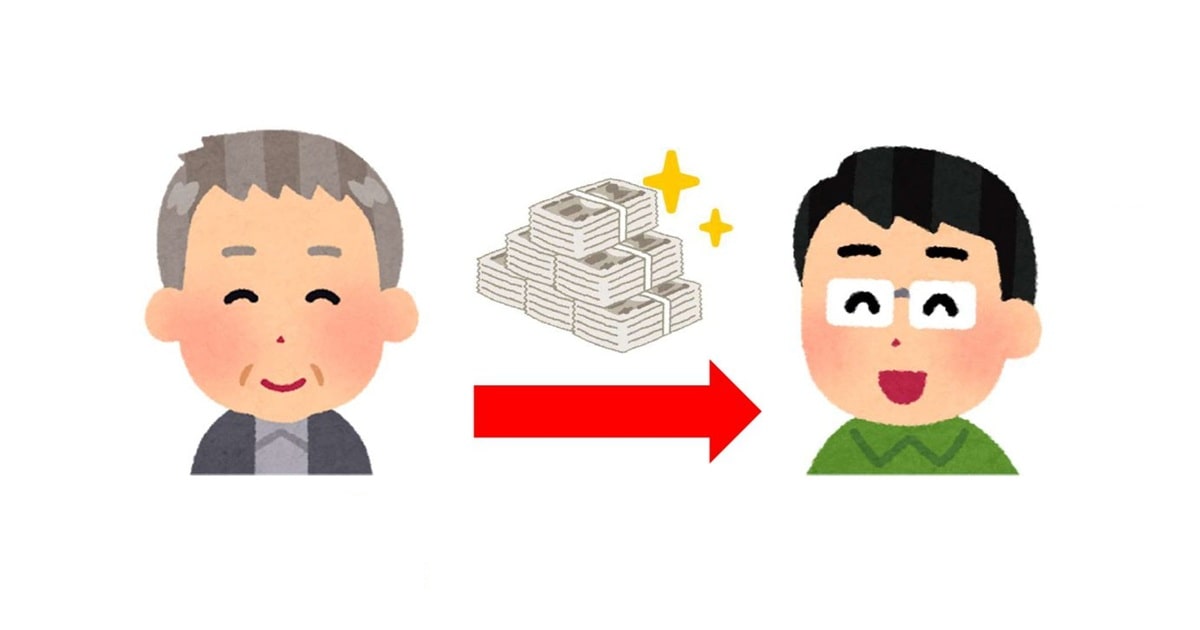相続税対策として、財産を生前贈与して相続財産を減らす方法があります。生前贈与には様々な特例がありますが、暦年課税制度と相続時精算課税制度はどちらか片方しか利用することができません。
この記事では、暦年課税制度と相続時精算課税制度の違いとメリット・デメリット、そしてどちらを利用すればお得になるのかをわかりやすく説明します。
暦年課税制度と相続時精算課税制度の違い
暦年課税制度を利用した贈与
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から暦年課税に係る基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。この場合、贈与税の申告は不要です。
相続時精算課税制度を利用した贈与
相続時精算課税制度では、累積贈与額が2,500万円までは贈与税が非課税となり、2,500万円超の部分は一律20%課税されます。ただし、相続時は累積贈与額を相続財産に加算して相続税が課税されます。納付済贈与税額は相続税額から控除・還付を受けることができます。
暦年課税制度と相続時精算課税制度の対比表
| 暦年課税制度 | 相続時精算課税制度 | |
| 贈与をする人 | 誰でも良い | 贈与をした年の1月1日において60歳以上である父母または祖父母 |
| 贈与を受ける人 | 誰でも良い | 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の推定相続人である子および孫 |
| 対象財産 | 制限なし | 制限なし |
| 贈与税控除額 | 贈与を受ける人ごとに年間110万円 | 上記の贈与をする人ごとに2,500万円(届け出提出後から相続するまでの合計) |
| 贈与税控除額を超えた場合の税率 | 通常の贈与税の累進税率10〜55% | 一律20% |
| 贈与税の申告 | 110万円を超えたら申告 | 相続時精算課税選択届出書を提出後のすべての贈与で申告 |
| 贈与をする人が死亡した場合の相続税 | 原則として相続財産に加算しない。ただし、相続開始前7年間に受けた贈与財産は相続財産に加算する。 | 相続時精算課税制度を適用した贈与財産は、贈与時の価格で相続財産に加算する。 |
| 贈与税が相続税を超えた場合 | 差額分は還付されない | 差額分は還付される |
| 利用制限 | なし | いったん相続時精算課税制度を利用すると暦年課税制度は利用できない |

ねこ
暦年課税制度は110万円を毎年コツコツ贈与する場合に向いていて、
相続時精算課税制度は不動産など大きな額の資産を贈与する場合に向いてるってことだね。

おくりん
その通り!
相続時精算課税制度のメリットとデメリット
暦年課税制度と比較した場合の相続時精算課税制度のメリットとデメリットを説明します。
メリット
- 不動産など大きな額の資産を贈与する場合に、贈与税控除額を超えた額にかかる税率が低い
- 財産の評価額が贈与時点なので、贈与時から相続時に価値が上がる財産を贈与する場合は相続税の節税効果がある
- 収益不動産を贈与すると、家賃収入が贈与を受ける人のものになり、贈与する人の相続財産を減らすこともできる
- 相続が発生する前に、贈与する人の意思で財産を分与できる
- 相続時に相続税がかからない場合は、早めに財産を贈与できる
デメリット
- 相続時精算課税選択届出書はいったん提出すると撤回できない
- 相続時精算課税制度を利用して不動産を贈与した場合は不動産取得税が課税されるが、相続時は課税されない
- 相続税が課税される場合、相続時までに財産を使い切って相続税が払えない場合がある
- 相続時精算課税制度を利用すると、小規模宅地特例を利用できなくなるため、相続税が高くなる場合がある
- 相続時精算課税制度を利用して贈与された不動産は物納できない

ねこ
どんな人が相続時精算課税制度を使えばいいの?

おくりん
将来値上がりする資産や、収益を生む不動産を贈与する場合に利用するとお得になります。
- 参考:国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
- 参考:国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択
関連書籍
リンク
リンク
リンク